東京の出生率は全国最低で、下がり続ける
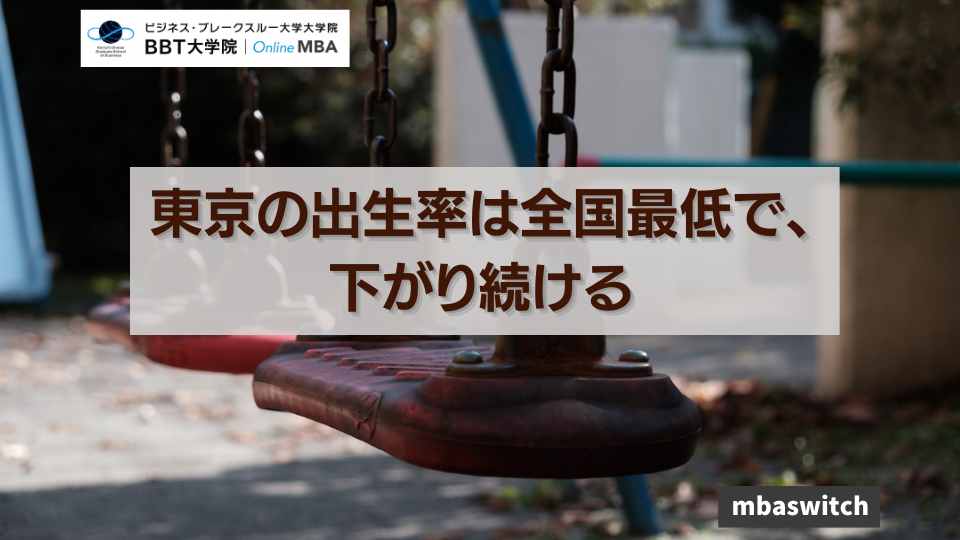
大前研一(BBT大学大学院 学長 / BOND大学教授 / 経営コンサルタント)
編集/構成:mbaSwitch編集部
日本の少子化が止まりません。厚生労働省が発表した人口動態統計月報年計(概数)によると、2024年に国内で生まれた日本人の子供の数は68万6061人で、統計を取り始めてから初めて70万人を下回りました。
【資料】令和6年(2024) 人口動態統計月報年計(概数)の概況
国家存亡の危機ですが、政治の動きは相変わらず遅く、先が思いやられます。東京都などが進めている婚活支援が実は逆効果であることが世界的にも指摘されています。BBT大学院・大前研一学長に少子化問題について聞きました。
家族の大切さを語るドラマも政治家もなくなった
年間出生数は2023年から約4万人減少している。合計特殊出生率は1.15で、前年の1.20を下回った。特に深刻なのは東京都である。東京都の合計特殊出生率は前年に初めて1を割り込んだが、2024年はさらに悪化して0.96まで下がった。この数字は全都道府県で最低である。
2014年、日本創生会議が「896の自治体が消滅する可能性がある」という「増田レポート」を発表して過疎地域の少子化に警鐘を鳴らした。出産する中心的な世代である20〜39歳の若年女性の人口動態から割り出したという。しかし、地方から若年女性が流入している東京都の出生率が全国最低なおかつ下がり続けているのだから、会議の座長を務めた増田寛也元総務大臣らの指摘はピントがずれている。若年女性を呼び込んだところで出生率が改善するわけではないのだ。
少子化には二つの大きな原因がある。順番にみてみよう。
(1)家族を大事にする風潮の衰退
一つ目の原因は家族を大事にする風潮の衰退である。なぜなのか。さらに掘り下げると以下の三つの原因が考えられる。
(1−1)ホームドラマは絶滅の危機
昭和はホームドラマの全盛期だった。テレビをつけると家族の絆を肯定的に描くドラマが放映されていて、視聴者はドタバタがありつつも家族が仲睦まじく暮らす姿に憧れたものだった。
しかし、今やホームドラマは絶滅の危機で、ドラマは警察や医療ものばかりである。そもそもドラマの番組枠も減っていて、芸人が並んで無駄話をしている番組ばかりになってしまった。テレビ離れも進んでいて、TikTokやYouTubeで趣味の動画ばかりが視聴されている。
テレビ番組の世界の話だけではない。かつては家庭を大事にしている政治家もいた。私は故・小渕恵三元総理と親交があって銀婚式に呼ばれたが、出席者に嬉しそうに家族を紹介していたのを覚えている。小渕氏は、私が経営に関わっていたお台場の商業施設ヴィーナスフォートにお忍びで訪れたこともある。彼の長女が手芸をやっていて、施設内のカートで販売していたのだが、一国の総理大臣が公務の合間を縫って一つ買いに来たのである。
(1−2)家族を大切にするイメージがない政治家たち
しかしそれ以降、歴代の総理大臣や知事など政治家から「家族が一番」「子煩悩だ」というエピソードを聞いたことがない。家族を大切にしているイメージが全くない政治家から「出生率を改善しよう」「結婚を増やそう」と言われても説得力がゼロである。
(1ー3)産業構造の変化
少子化は産業構造が変化した影響も大きい。戦後間もない日本は、働く人の約半分が農業に従事していた。昔の農業は完全な労働集約型産業で、人手は多いほどよかった。ゆえに早く結婚して、子供をたくさんつくって農作業を手伝わせていた。2022年の民法改正までは、女性は男性よりも早い16歳から結婚できたのもその名残りだった。
しかし、今や農業人口は総人口の約1%に過ぎない。数少ない農家はほとんど高齢者で農作業を機械でやっている。代わりに工業やサービス業が台頭して、働く人の多くが勤め人になった。農家のように自営業でなければ、子供をつくっても労働力にならない。それどころか、共働き夫婦にとっては子供を持つことが経済的負担になり、キャリア形成のハンディキャップにもなりうる。世帯単位で見た場合、子供を産み育てることに経済合理性がなくなってしまったわけである。
(2)婚活のデジタル化
少子化にはもう一つ見逃してはいけない大きな原因がある。婚活のデジタル化である。
今の若者には信じられないかもしれないが、昭和は女性をデートに誘うのも一苦労だった。連絡手段は手紙か家の電話のみ。家の電話にかけると父親が出ることもあり、その関門を突破しないと本人に取り次いでもらうこともできない。スマホ時代なら「今からどう?」といった気軽な誘い方ができるが、当時は事前に段取りを決めてからでないとデートが成立しなかった。
とにかく1回のデートに手間がかかるので、3〜5回デートするうちには結婚に相応しい相手かどうかを品定めし、結婚を前提とした交際に発展していった。相応しくないと思えば、また別の女性にデートを誘うところからやり直さなくてはいけない。それが負担なので、それなりのところで妥協する人は少なくなかった。親や仲人さんの圧力でお見合い結婚する人も多くいた。
一方、今はマッチングアプリで婚活する時代で、AIが提案する候補の写真とプロフィールを見て気に入った相手と簡単にデートできる。出会いのハードルが下がったなら結婚の数は増えそうなものであるが、気軽に会えるがゆえに「もっといい人と出会えるかも」と妥協できなくなってしまう。
勢いで結婚した後の離婚のハードルも下がった。婚活が労働集約型だった時代は「離婚したらまた再婚相手を探すのが大変」「仲人さんに顔が立たない」とブレーキがかかるが、マッチングアプリならすぐに再婚相手を探せると考える。候補がたくさんいれば、結婚の決断は遅れる一方で、離婚の決断は速くなってしまう。非婚化・晩婚化・離婚早期化が進めば、おのずと出生率は低下する。こうした現象は世界的な潮流で、米国の週刊誌「Newsweek」の表紙や特集でもマッチングアプリの弊害が取り上げられていた。
こうした事情も調べずに、合計特殊出生率ワーストの東京都は2024年9月から、婚活支援のたAIでマッチングさせるアプリ「TOKYO縁結び」を運用している。都はアプリを含む結婚支援事業には3年間で計8億円の予算を充てる計画である。小池百合子都知事は少子化対策の取り組みとしてPRしているが、勘違いも甚だしい。婚活支援としては逆効果で、東京都の少子化は加速するだろう。
日本の戸籍制度は廃止したほうがいい
税金を無駄遣いしてまでマッチングアプリをつくることより取り組むべきことがある。戸籍の廃止である。
まず、婚外子の問題がある。日本では父親の戸籍に入らない子供は「非嫡出子」とされ、法的に権利が制限され、社会的にも差別的な扱いを受けてきた。未婚の出産、育児は母子ともにハンディがあるため、中絶が選択されがちなのである。婚外子の差別の温床となる戸籍制度を運用している国と地域は、現在、世界でも中国・台湾だけである。韓国は、2002年に廬武鉉氏が大統領選挙の公約に戸籍廃止を掲げて当選し、2008年に男女差別の温床になっているとして廃止した。
そもそも日本の戸籍は、皇居の「東京都千代田区千代田1番」と指定する人が多く、私が住む千田区行政を圧迫する困った問題になっている。2025年は戸籍のフリガナ登録を進めているが、デメリットしかない時代錯誤の戸籍法は韓国同様、即廃止すべきである。
戸籍があるせいで、日本では「血がつながっているか」を重視する傾向が強いが、欧米と比較すると異常である。先進国の中では出生率が比較的高いフランスは、生まれてくる子供の約6割が婚外子である。米国は約4割、英国は約5割、ドイツ・イタリアでも3割強である。一方で、日本は約2%である。
ちなみにフランスには、子供が多いほど税金が安くなる仕組み(N分N乗方式)がある。またスウェーデンでは子供が多いと広い家に住めるように家賃補助が出る。出生率が2に近い先進国は、子育て世帯への経済的な支援も充実している。
ただ、少子化対策優等生と言われた北欧諸国やフランスも、ここ数年は出生率が再び低下傾向にある。経済的支援の効果はせいぜい20年であり、少子化の大きな流れは断ち切れなかった。それでも、なすすべなく落ちていった日本と違って、いったん引き上げた北欧諸国やフランスにはまだ余裕がある。
国や都の政治家は、婚活支援や戸籍のフリガナといった日本を衰退させる政策はやめるべきである。海外の事例を学び、差別の撤廃を一刻も早く断行し、少子化問題に取り組んでもらいたい。
※この記事は、『プレジデント』誌 2025年8月1日号 を基に編集したものです。
大前研一
プロフィール マサチューセツ工科大学(MIT)大学院原子力工学科で博士号を取得。日立製作所原子力開発部技師を経て、1972年に経営コンサルティング会社マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社後、本社ディレクター、日本支社長、アジア太平洋地区会長を歴任し、1994年に退社。スタンフォード大学院ビジネススクール客員教授(1997-98)。カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)公共政策大学院総長教授(1997-)。現在、ビジネス・ブレークスルー大学学長。豪州BOND大学教授。



