トランプのイラン核施設攻撃が、全世界に影響を及ぼす
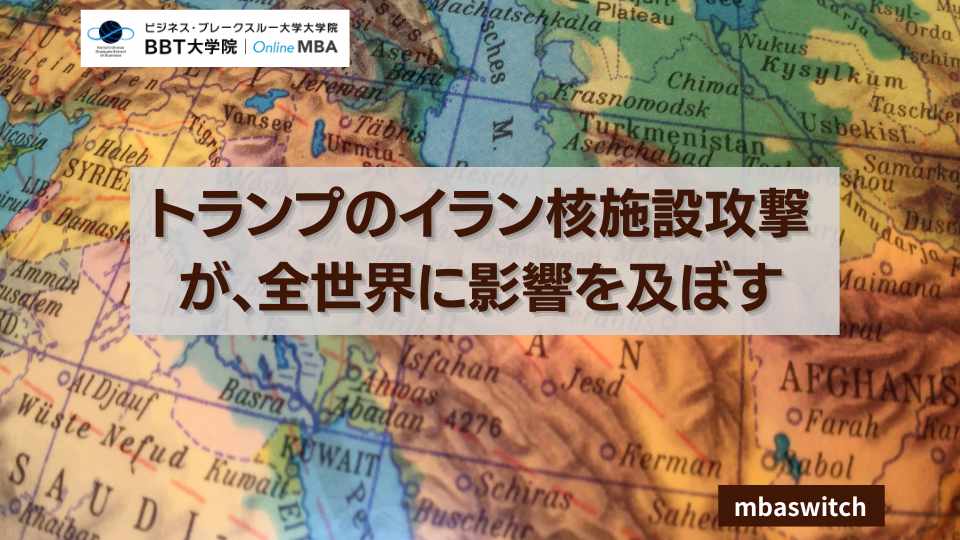
大前研一(BBT大学大学院 学長 / BOND大学教授 / 経営コンサルタント)
編集/構成:mbaSwitch編集部
2025年6月21日、米国がイランの核施設に空爆を行いました。被害は甚大で同年6月13日から続いていたイスラエルとイランの「12日間戦争」は同年6月24日に停戦合意に至しました。「この空爆は世界の地政学に大きな変化をもたらす」とBBT大学院・大前研一学長は指摘します。どのような変化なのでしょうか。日本は変化についていけるのでしょうか。大前学長に聞きました。
イスラエルがイランに戦争を仕掛ける
今回の12日間戦争の背景にあるのはイランの核開発だった。核開発を進めていたイランは2015年、米欧諸国が課していた経済制裁の解除と引き換えに核開発の制限に合意した。合意には米英独仏中ロの6か国が参加していたが、2018年に第1次トランプ政権の米国が離脱した。それを受けてイランは核開発を再び加速していた。
合意が完全に反故になったわけではなく、国際原子力機関(IAEA)による査察は続いていた。しかし、査察が機能せず、イランはウランの濃縮度を60%まで高めていた。
それに我慢がならなかったのがイスラエルである。イスラエルは核保有国である。イランが核兵器を完成させれば自国の優位性がなくなってしまう。ただ、イスラエルにはイランの地下約100mにある核施設を破壊できる兵器がない。そこで、米国を巻き込もうとネタニヤフ首相は戦争を仕掛けた。
実は核弾頭を作っても、ミサイルで飛ばして敵地で爆発させるのは容易ではない。イスラエルはフランスに技術を教えてもらって核兵器を完成させたが、イランに技術を教える国はない。それを考慮すればイランの核兵器完成にはまだ時間的な猶予はあった。しかし、イランの支援を受けていたパレスチナのイスラム組織ハマスはほぼ壊滅し、レバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラも弱体化した。シリアのアサド政権も倒れている。「イランを攻撃するなら今だ」ということで、攻撃に踏み切った。
これに米国も呼応した。米国はベトナム戦争以降、お粗末な軍事作戦が続いていた。しかし今回は、イスラエルの情報機関モサド(イスラエル諜報特務庁)からもらった情報をもとに周到な用意をして爆撃を成功させた。
米国が誇る地下貫通弾(バンカーバスター)は地下約60mまでしか破壊できず、重要施設は無事だという分析もある。しかし、1回で届かなくても2回、3回と打ち込めば地下100m以上でも関係ない。
注目すべきは空中給油を成功させたことである。当初、ステルス爆撃機はミズーリ州の基地からグアムに向かったとされていた。ところが、こればフェイントで、米国本土からイランに直接向かっている。その際に問題となるのがステルス爆撃機の航続距離である。バンカーバスターは1発約13tでそれを2発積むと航続距離が短くなる。直接向かうには空中給油機を出して密かに給油する必要がある。米国はそれを苦も無く成功させた。
なぜイスラエルの誘いに米国が乗ったのか
それにしても、なぜ米国はイスラエルの誘いに乗って空爆したのか。最大の理由はノーベル平和賞である。馬鹿げたことであるが、ドナルド・トランプ大統領は本気でノーベル平和賞を欲しがっている。そのためには「俺が世界を平和にした」と演出する必要があった。
演出の方法は単純である。トランプ大統領は「アプレンティス」と言うリアリティショーの司会で有名になった。その番組では最後のいいところで登場して「You’re fired!(おまえはクビだ!)」と決め台詞を発して盛り上げる。12日間戦争も同じで、最後に自分の出番を持ってきて目立とうとした。
イスラエルは12日間戦争でイラン革命防衛隊トップを含む要人を次々に爆殺している。おそらくモサドは最高指導者ハメネイ師の居場所も掴んでいて、いつでも攻撃できたはずである。
その状況を理解していたハメネイ師は、急遽、高位聖職者3人を後継者候補に指名した。実はその中にハメネイ師の息子は含まれていない。自分が暗殺されるどころか、死後に後継者まで殺されることまで覚悟していたからこそ、息子を後継者候補のリストから外していた。
ところが、トランプ大統領はイスラエルにハメネイ師暗殺をストップさせた。情けをかけたわけではない。バンカーバスターを落とす前に、レジームチェンジ(体制転換)が起きてしまえば、自分の出番がなくなるからである。
戦後の日本と同じことがイランでも起きる
米国とイスラエルの軍事的勝利で、今後イランはエジプト化していくことが予想される。
エジプトは第二次世界大戦後のアラブ世界の盟主であり、イスラエルとも激しく対立していた。しかし、4回の中東戦争でコテンパンにやられて、反イスラエルの旗を降ろさざるをえなくなった。友好的だとは言わないが、イスラエルがエジプト経由でさまざまな物資の輸出入を行うなど、現在は一般的な国同士の付き合いをしている。イランが今回の敗北でどこまでレジームをチェンジするのかはわからないが、少なくとも、エジプトと同じく、反米、反イスラエル政権ではなくなる。
「米国とイスラエルにコケにされてイランが黙っているわけがない」と考える人もいるだろう。我々日本人も第二次大戦中は「鬼畜米英」と米国人を罵っていた。にもかかわらず、終戦した途端に米英礼賛に180℃変わった。おそらく、イランでも戦後の日本と近いことが起きる。
もともとイランはパーレビ国王時代、親米寄りだった。石油のおかげで経済は良く、国民生活も豊かだった。足の見えるスカートはく若い女性もいたほどである。しかし、西欧的な生活はイスラム原理主義者には堕落に映る。そこで1979年にホメイニ師が革命を起こして国王は亡命した。その後、米国大使館を占拠したため、米国、イラン両国の関係は悪化した。
その後、宗教的全体主義で国民も反米化したが、本音では王政時代の生活を懐かしむ人も多い。イラン国民の意識もエジプト化する中で変わっていくだろう。
また、「今回の核の破壊は十分ではなかった」との分析があるが関係ない。兵器開発を加速すればまた攻撃される。イランはそのようなリスクをおかさない」という読みをしなくてはならない。
世界の地政学のバランスが大きく塗り替わる
変化するのは中東だけではない。今回の空爆成功は、地政学のバランスを大きく塗り替えてしまった。
まず、中国が台湾を軍事的に攻略するリスクが下がった。中国軍は対米軍の空母対策をしっかりとやってきた。しかし、ステルス爆撃機でバンカーバスターを運んできて、北京中枢を破壊するような攻撃への備えは不安が残る。今から備えるとしても、習近平国家主席の残り3年のうちに整えるのは難しい。
北朝鮮の金正恩最高指導者は今ごろ青い顔をしているに違いない。核開発をやめない北朝鮮に対して、第1次トランプ政権は金正恩最高指導者をピンポイントで攻撃する「鼻血(ブラディ・ノーズ)作成」を立案したことがある。イランへの空爆により、鼻血作戦がいつでもできることが証明された。第1次トランプ政権は北朝鮮と話し合う姿勢を見せたが、今のトランプ大統領は悠長に交渉しない可能性がある。
新しく就任した韓国の李在明大統領は北朝鮮に宥和的なスタンスである。しかしその姿勢を強調すると韓国自身が脅威とみなされるおそれもあり、難しい判断を迫られる。
欧州ではロシア・ウクライナ戦争の終結が近づいた。ロシアはイランからドローンの提供を受けていたが、イスラエルのイラン攻撃には何も支援できなかった。プーチン大統領はイランの現状をみて、これ以上は欲張れる立場にないと痛感したはずである。
一方、ウクライナに対してはトランプ大統領は急に方針転換して軍事支援をすると言い出している。イラン攻撃の成功を受けて、ノーベル平和賞のためにさらなる実績が欲しいというトランプ大統領の本音がうかがえる。
NATO(北大西洋条約機構)も方針変更を余儀なくされる。欧州諸国は国際協調主義をとっていて、ロシアの現実的な脅威への対応は米国任せにしてきた。しかし、今回のイラン核開発でIAEAや国連の無能ぶりが際立ち、話し合いによる平和が幻想であることが明らかになった。最後は武力で解決するしかないという現実をつきつけられたのである。
NATOとしても、今後はトランプ大統領のご機嫌をとって引き留めつつ、米軍が去った場合に備えて軍備を強化する二本立ての政策をとらざるをえない。2025年6月のNATO首脳会議で各国の国防費支出を2035年までに対GDP比5%に引き上げる目標を掲げたのもその一つである。
日本の外交の在り方を再定義する必要がある
一方、日本は今も国連中心の平和外交そして日米同盟頼みの国防を基本方針にしている。しかし、話し合いによる平和は非常に脆く、米国は気分屋で日本を本当に守ってくれるのかどうかわかない。そうした現実が明らかになった以上、日本は中国や韓国、ロシア、米国、それぞれとの関係を見直して、外交・安全保障のあり方を再定義しなければならない。
ところが今回の参議院選挙でもバラマキの話ばかりで、外交・安全保障は争点にされていない。地政学の大きな変化から日本が取り残されており、非常に心配である
※この記事は、『プレジデント』誌 2025年8月15日号 を基に編集したものです。
大前研一
プロフィール マサチューセツ工科大学(MIT)大学院原子力工学科で博士号を取得。日立製作所原子力開発部技師を経て、1972年に経営コンサルティング会社マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社後、本社ディレクター、日本支社長、アジア太平洋地区会長を歴任し、1994年に退社。スタンフォード大学院ビジネススクール客員教授(1997-98)。カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)公共政策大学院総長教授(1997-)。現在、ビジネス・ブレークスルー大学学長。豪州BOND大学教授。



