石破総理と小泉農水大臣に農政改革の推進を期待する
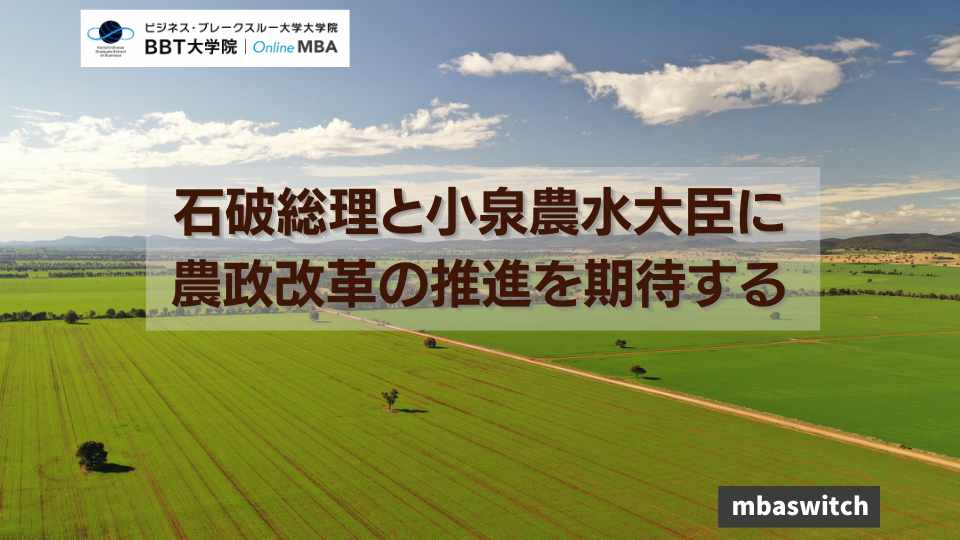
大前研一(BBT大学大学院 学長 / BOND大学教授 / 経営コンサルタント)
編集/構成:mbaSwitch編集部
米の価格高騰で一時は大騒ぎになりました。2025年6月からは備蓄米が店頭に並び始め、ようやく落ち着く気配を見せ始めました。備蓄米放出の指揮を執った小泉進次郎農水大臣にとっては、政治家になって初めてのお手柄であり、どこか得意げに見えます。小泉大臣の「農協外し」が成功している裏事情をBBT大学院・大前研一学長に聞きました。
農協の機能不全が露呈
振り返ると、2024年5月には米の店頭価格は5㎏2100円前後だった。しかし徐々に品薄になり高騰した。生産量や消費量に大きな変化はないため、いずれ落ち着くと思われたが、2025年3月には4000円台に値上がりした。約1年でほぼ2倍の価格に値上がりした。
そこで政府は2025年3月、不作に備えて保管している備蓄米の放出を決定した。ただ、その競争入札のやり方が悪かった。政府は放出米に1年(後に5年に変更)を期限とする買戻し条件をつけたのである。買戻し条件をつけたのは、備蓄米放出で逆に米が余り、想定以上に価格が下がることを避けるためである。
ただ、いったん買ったものを「後で返せ」と言われると、普通の集荷業者は入札に参加しにくい。実際、入札に参加できる業者は限られ。初回入札では全国農業協同組合連合会(JA全農)が9割以上を落札した。従来と同じように農協が大部分を落札すれば、流通の流れは何も変わらない。やはり店頭価格は下がらなかった。
そうしたタイミングで、江藤拓農水大臣(当時)が「米は買ったことがない。支援者の方々がたくさん米をくださり、売るほどある」と失言して更迭された。代わって登板したのが小泉大臣だった。
石破茂総理の指示で、政府は備蓄米を随意契約で小売業者に販売することを決定。実は小泉大臣は総理の指示に従っただけだったが、総理でさえ「3000円台」と言っていたところを、小泉大臣は「2000円前後」と言い切った。いつもは空回りして「ポエム大臣」などと揶揄されていたが、今回は歯切れよく、短い言葉で伝えているから不思議と冴えて見える。
とはいえ、最初から随意契約にしていれば、もっと早く価格は落ち着いたはずである。その意味では政府は対応が不十分だったが、良かったことが一つだけある。それは農協の機能不全が露呈したことである。農協中心の流通で米の価格は上がり続け、農協を外すと下がる。政府の対応の不十分さから、この事実を目の当たりにして、国民の多くは農協の存在意義に首を傾げるようになったのである。
小泉大臣の「農協外し」を財務省が応援する裏事情
戦後、日本の就労人口の約半分は農家だった。当時なら農家の協同組合である農協にも意義があった。しかし、農業従事者は今や全人口の約1%の116万人(2023年)に減った。それに合わせて縮小すればまだわかるが、農協は全国に500以上もあり、職員数は約17万人もいる。116万人の農家を支えるために、これだけ多くの職員がいるのはサイズオーバーである。
農協は農家でなくても加入できる。非農家の准組合員を加えると、組合員数は1000万人以上いる。農業従事者の10倍近い組合員数がいるのは、組合員になるとローンを有利な条件で組めたりガソリンの価格が安くなるからである。多くの人が農協という巨大組織に寄りかかっている。
実は農協に寄りかかっていた存在がもう一つある。自民党である。かつての自民党は農協を集票組織として頼っており、見返りとして農家を保護する補助金制度を整えてきた。しかし、農業人口がここまで減ると集票力は衰える。准組合員が多いといっても、准組合員は生産者というよりむしろ消費者の側面が強い。もはや自民党として農協を守るメリットは少ない。
父親が郵政民営化を行ったDNAが受け継がれているのか、小泉農水大臣はそのことをわかって農協外しに踏み切ったのである。「備蓄米を売り出したら、いざというときの備蓄米がなくなる」と騒ぐ族議員や野党の攻撃に対して、小泉大臣は「海外からの(無関税の)ミニマムアクセス米の入札を早める」と脅している。
さらに財務省は、2025年7月に実施される参院選の選挙対策として消費税に手をつけようという与野党の、”危険分子”を封じ込めるためにも、物価への影響が大きかった米価格を下落させるのに、小泉応援団を演じた。つまり、今回は一人でポエムを読むのではなく、強力な応援団がいたのである。
食料自給率はなぜデタラメが
農協が弱体化すれば米農家が困って廃業が相次ぎ、結局は消費者の首を絞めることになるという声もある。しかしそれは大間違いである。
「米農家を守れ」という根拠の一つに、食料自給率をあげる論者は多い。「米は日本人の主食であり、100%自給していないと、いざというときに困る」というわけである。ただ、稲作には水田に灌漑用水を引くポンプやトラクターなどの農機が欠かせない。機械は電力は電力やガソリンで動くが、日本の石油備蓄は国家備蓄・民間備蓄などを合わせても240日分程度である。化学肥料も化石燃料などを原料としている。
米の自給率が今年100%でも、エネルギーが枯渇すれば次の年は作れなくなるし、消費者は炊飯器を使えずに生米を噛むしかなくなる。そのような問題を無視して、米だけ自給率100%をうたうのは滑稽である。米の消費量は年々減少しているし、若者の好きなパンや麺類の原料である小麦の自給率は17%に過ぎない。
食料安全保障を本気で心配するなら、むしろ政府は市場を開放して、外交的努力で、多様で安全な輸入ルートを確保することにこそ力を入れるべきである。
日本は農政改革を進めるべき
「海外産のコメはおいしくないから開放しても日本人は誰も食べない」という意見も、実際に最近の海外産の米を食べたことがない人の思い込みに過ぎない。
最近、注目を集めている「カルローズ」は米カリフォルニア州で主に栽培されているジャポニカ系中粒米種で、普通においしい。なかでも日本人が渡米して開発した「国宝ローズ」という品種は、現地の日本人駐在員に人気が高く、日本の家族に食べさせようとお土産で買って帰る人もいるほどである。
海外産の米の魅力は味だけではない。海外の稲作は大規模で効率が高いため、とにかく安い。
私の知人が、オーストラリアのビクトリア州で年間30万トンの米(品種はコシヒカリ)を生産している。水田の大きさは幅6㎞×長さ30㎞。30kmといえば東京駅から横浜駅までの距離であり、まさに見渡す限りすべて水田である。広大な土地に水を引くのは大変だというのは国土が狭い日本の発想である。その農場では、モーターグレーダーという建設機械を使って100mごとに約2cmの勾配をつけて水が行き渡るようにしている、苗は一つ一つ植えない。飛行機で種を直播きするだけである。
農薬や肥料を使わない。手間はかからないが「収穫量が落ちるのではないか」と質問したら「鳥が来て食べていくが、鳥は満腹になればよその土地に飛んでいく。虫や病気を含めても9割は無事」と気にしていなかった。
そうやって手間暇かけずに大量に生産するからコストは安い。価格を聞いたら「5000円」という、5㎏5000円は「日本より高い」と驚いたが、よく聞いたら1t5000円だった。単位からして違うのである。日本の農業は効率が悪すぎることを認めざるをえない。
安いお米が入ってきたら国内の農家はやっていけないという人もいるが、それも農家次第である。
私は「Oh my BBT米」と銘打った、五郎兵衛米のブランド米を長野県佐久市(旧浅科村)で生産している。あの辺の農家は、農協を通さず、減農薬のブランド米を道の駅に持ち込み、自分でつけた値段で売っている。今のように米価格が高騰する前で、だいたい5㎏5000円前後の値付けをしていたが、夕方にはいつも売り切れていた。ネット通販などでも販売している。付加価値をつければ安い米とは競合せずにしっかりと利益が出るのである。
今回の備蓄米騒動で農協の機能不全が明らかになったため、今後は道の駅やネット販売、飲食店や小売りとの直接取引など農協を通さない米の流通が拡大していくだろう。
そもそも消費者にとっては「世界の最適地で生産したおいしくて安い米」が販売されることこそが利益である。それは米に限らない。たとえば牛肉ならアルゼンチンの赤肉、豚ならデンマークとポーランド、鶏ならウクライナなど、世界には本当においしい肉の生産地がある。日本であまり知られていないのは、国内畜産業を保護するために参入障壁を設けてきたからである。市場を開放したら、海外産は安くておいしいから、非効率ゆえに高い国内産はすぐに消費者からそっぽを向かれる。日本の消費者は、おいしいものを安く食べるチャンスを奪われてきたのである。
ここまで言っても、「国内産は安全・安心だから」という人もいる。しかし、日本は世界有数の農薬大国である。輸入品でも国産品でも安全性は大差ない。
トランプ大統領は関税政策で米国経済を停滞させ、世界各国と対立を招いている。日本はトランプ関税を反面教師にするべきである。世界の最適地で生産して輸入することこそが、国民生活を豊かにする。ここまで良いところなしだった石破総理や小泉大臣には、今回の混乱を契機に、ぜひ日本の農政改革を進めてもらいたいものである。
※この記事は、『プレジデント』誌 2025年7月18日号 を基に編集したものです。
大前研一
プロフィール マサチューセツ工科大学(MIT)大学院原子力工学科で博士号を取得。日立製作所原子力開発部技師を経て、1972年に経営コンサルティング会社マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社後、本社ディレクター、日本支社長、アジア太平洋地区会長を歴任し、1994年に退社。スタンフォード大学院ビジネススクール客員教授(1997-98)。カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)公共政策大学院総長教授(1997-)。現在、ビジネス・ブレークスルー大学学長。豪州BOND大学教授。



