新たな日本国憲法をゼロベースで起案すべき
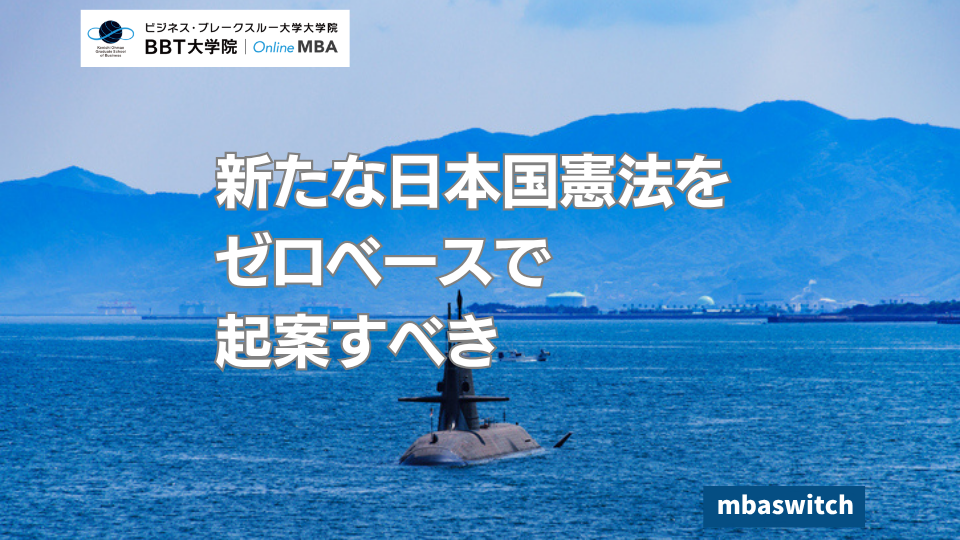
大前研一(BBT大学大学院 学長 / BOND大学教授 / 経営コンサルタント)
編集/構成:mbaSwitch編集部
2025年10月、臨時国会における首相指名選挙で、自民党総裁の高市早苗氏が第104代首相に選出される見通しです(2025年10月20日時点)。高市氏は憲法9条の改正論者です。憲法9条の改正に関する論議が盛り上がるのでしょうか。一方、「日本の『戦後』を終わらせるためには憲法を改正するのではなく、新たな憲法をゼロベースで起案すべき」とBBT大学院・大前研一学長は主張します。
日米安保中心の外交を見直すべき
2025年は戦後80年を迎える節目の年である。戦争体験の風化を憂う声もあるが、私はむしろ日本が80年前から何も変わっていない点に不安を覚える。時代は大きく変わっているのに、国家像は戦後あわただしく構築したままで、その後、手を入れていないのだ。
わかりやすいのは安全保障だろう。日本は敗戦で連合国に完全武装解除をされ、憲法によって戦力不保持を規定された。その後、朝鮮戦争を機に、共産主義の脅威を恐れた米国の思惑で1950年に警察予備隊が組織され、自衛隊に発展した。ただ、憲法はそのままだから、自衛隊はいまだ国内で軍隊として位置づけられず、空母打撃群が持てないなど、大きな制限がある。
戦後、日本は国連中心の平和主義外交で、安全保障の基軸は日米安保条約に置いてきた。自衛隊に制限があっても、国連や米国が頼りになれば問題はまだ少なかった。しかし、ロシアのウクライナ侵攻、イスラエルによるガザ地区への攻撃を見てもわかるように、もはや国連は国家や地域の紛争に何の役目も果たせていない。
アメリカも、トランプ大統領には理念がなく、言っていることが日替わりでコロコロと変わる。今のところトランプ大統領は日米安保に強い関心を持っていないが、安全保障が「日替わりメニュー」では、それを基軸に国防を考えるわけにいかない。このように環境が変わっているのに、日本の外交・国防のシステムは戦後体制のままなのだ。
同じ敗戦国でもドイツは違う。ドイツも連合国に完全武装解除をされたところから再出発したが、10年後には正式な軍隊であるドイツ連邦軍が再編成された。その後、EUやNATOの枠組みに入って自動的に変わったところが大きかった。
NATOは米国のほかに英国とフランスという国連安全保障理事会常任理事国(=核保有国)と同盟を結んでいることもある。ドイツ連邦軍はNATOの核シェアリングの下、核兵器を武装、使用する準備をしている。
同じく敗戦国だったイタリアも、ドイツほど裁量が大きくはないものの、正式な軍隊を持っている。日本が外交や国防に関してどのような構想を持つべきかは議論の余地がある。ただ、国連中心の平和主義外交が通用せず、日米安保も頼りにならないという現実に目を向けなければ議論も始まらない。
憲法で、統治機構が十分に定義されていない異常性
日本の安全保障が時代の変化に適応できない要因の一つが憲法である。占領軍によって草稿された日本国憲法は当時のGHQの意向が反映されている。再軍備を禁じたのは日本へのお仕置きのようなもの。ところが護憲派は、「9条があるおかげで平和が守られた」と、ペナルティをありがたがっている。文章のみで平和が守られた前例は世界に一つもない。
世界に目を向ければ、憲法改正はとくに珍しいものではない。第2次世界大戦後に限っても、米国は6回、フランスは2回、同じ敗戦国でお仕置きされたドイツに至っては69回、イタリアも20回の改正を行っている。戦後、憲法改正の発議すら一度も行われていない日本のほうが異常なのだ。
見直したほうがいいのは9条だけではない。むしろ現行憲法の最大の問題点は、国家を形づくる「統治機構」がきちんと定義されていないことにある。会社でいえば組織図がない状態だ。
日本は江戸時代以降、中央集権で統治されてきた。とくに明治以降は天皇を中心とした強烈な中央集権・専制主義体制のもとで国家が運営されてきた一方、13州のUnited Statesとして建国された米国は連邦制国家で、中央集権を経験したことがない。こうした歴史の違いが、現行憲法の構造にも表れている。第8章「地方自治」では「地方公共団体」と呼ばれるにすぎず、自治に必要な立法、司法、行政の三権が付与されていない。
例えば9条には、地方公共団体は「法律の範囲内で条例を制定することができる」とある。中央の法律の範囲内しか条例を制定できないのだから、地方が独自にできることはほとんどない。驚くべきは、都道府県や市町村の違いすらどこにも定義されていないことだ。実際、「都」「道」「府」「県」の間に権限や財源上の違いはない。大阪維新の会が大阪都構想を打ち出したのも、大阪は「府」でなければいけないという決まりはないからだ。
最近、維新の会がまた「副首都構想」を打ち出している。そもそも東京都は、「あそこは東の京都です」といって名づけられたとも言われる。つまり、大阪は京都や奈良と合併して「本京都」と名乗ればいいのだ。都道府県の定義がないのだから、どう名乗ろうと、どこと合体しようと自由である。
実は「市」「町」「村」も、大きく権限は変わらない。人口規模によって名称は変わるが、町になる基準は都道府県によって違うし、基準を満たしていても「村のままでいい」と変更していないところもある。都道府県や市町村の定義があいまいだから、得体の知れない運用がまかり通っている。
憲法は改正するものではなくゼロから起案するものだ
人口減少期に入った日本には、地方再生が大きな課題だ。詳しくは拙著『君は憲法第8章を読んだか』(小学館)を参照してもらいたいが、地方公共団体がしっかり定義されておらず、自治権が与えられていない現行憲法のもとでは、できることは限られている。連邦制の米国は州によって法律が違い、税金さえも自由に決められる。イーロン・マスク氏がテスラ本社をテキサス州に移したのは、税金が安いからだ。そうやって州ごとに自分で繁栄する方法を考えて切磋琢磨するから、地方でも発展するところが出てくる。
ドイツは純粋な連邦制をとっており、16の州はそれぞれ議会・政府・裁判所を備え、三権が与えられている。そのため、州ごとに独自の制度や政策を展開し、互いに発展を競い合っている。
地方にどれだけ自治が与えられているかは、オーストラリア国内を移動すればよくわかる。実はオーストラリアは州ごとに時間を決めることができる。ブリスベンのあるクイーンズランド州は一年中同じ時間だが、南下してシドニーのあるニューサウスウェールズ州に入るとサマータイムで夏は1時間ズレる。さらに南下したところにあるメルボルン(ビクトリア州)もサマータイムだが、オーストラリア大陸西海岸のパース(西オーストラリア州)はサマータイム制を廃止した。旅行者には面倒だが、地方それぞれが「うちはこれで繁栄する」と決めた結果なのだ。
日本も中央集権の名残が強い統治機構を見直して、地方に権限を与えるべきである。具体的には、統治機構は少なくとも三階層に分けたい。
まず、外交や国防、金融政策など国家単位で動く必要があるものは中央政府が担う。それ以外の中央がやっているものは、道州制を導入して北海道や関西、九州など9つ程度の行政単位でやっていく。
もちろん、三権もできるだけ付与する。例えば現在、日本はどこでも文科省が決めた学習指導要領どおりに教育を行っている。第1外国語として英語は必須だが、第2外国語は地方に任せたい。
北海道ならロシアとの取引があるだろうし、日本海側や九州北部なら韓国語が使えるほうがいい。同じ九州地方でも沖縄や奄美は東京より台湾のほうがずっと近い。経済圏を東シナ海で形成したほうが道理にかなっているから北京語が役に立つ。このように地方によって一緒に繁栄したいパートナーは違うのだから、それに合わせて外国語教育も変えるべきだ。
その下の基礎自治体には地域により即した自治権を与える。例えば建築基準は基礎自治体単位で決めればいい。日本の国土は東西と南北の幅がそれぞれ約3,000kmで、地方ごとに気候は大きく異なる。また、同じ地方でも山側と海側では地盤や災害リスクが違う。それに合わせてきめ細かく建築基準を定めるべきだが、現在は全国一律だ。
建築家の安藤忠雄氏は古くからの友人で、私が入る予定のお墓も設計してくれるほど仲がいいが、最近は日本の法令に不満を持っているようだ。優れた構想を描いても、制約があって実現できないことが多いという。最近の安藤氏はドバイやモナコのような王族の仕事が増えているらしい。王様なら建築基準も思いどおりになるからだ。
地方を象徴するような名建築をつくりたくても、全国一律の建築基準法が邪魔して世界レベルの建築家らに敬遠されているとしたら、これほど馬鹿らしいことはない。訪日外国人に建築基準法のなかった戦国時代の「お城」が人気があるが、それぞれが名将の構想で独自色に溢れているからではないか。もちろん安全を軽視してはいけない基準は地域に決めさせればいい。
統治機構をこのように抜本的に改革するならば、もはや憲法改正では対応できない。現行憲法を手直しするのではなく、ゼロベースで新たに憲法を考えるべきだ。国民の一人一人がアメリカ独立宣言を起草したトーマス・ジェファーソンになったつもりで、この国に必要なものを白い紙に書きだすのだ。
「占領軍の置き土産の憲法をどのように解釈するか」で議論しているうちは、時代の大きな転換点に対応できない。政治家には大局観を持ってこの国のあり方をゼロベースで考えてもらいたい。
※この記事は、『プレジデント』誌 2025年10月3日号を基に編集したものです。
大前研一
プロフィール マサチューセツ工科大学(MIT)大学院原子力工学科で博士号を取得。日立製作所原子力開発部技師を経て、1972年に経営コンサルティング会社マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社後、本社ディレクター、日本支社長、アジア太平洋地区会長を歴任し、1994年に退社。スタンフォード大学院ビジネススクール客員教授(1997-98)。カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)公共政策大学院総長教授(1997-)。現在、ビジネス・ブレークスルー大学学長。豪州BOND大学教授。



