「石破おろし」はなぜ実現が難しいのか?
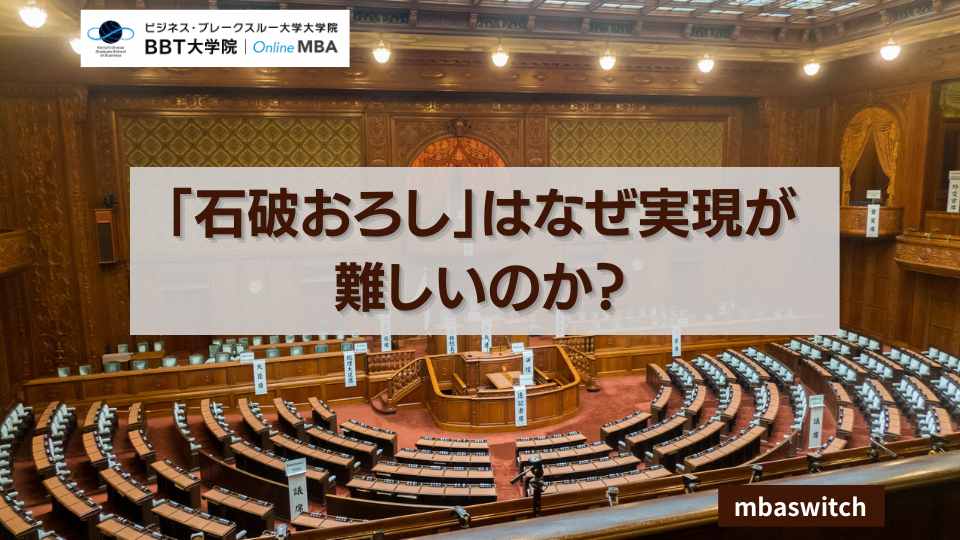
大前研一(BBT大学大学院 学長 / BOND大学教授 / 経営コンサルタント)
編集/構成:mbaSwitch編集部
2025年7月の参議院選挙で、自民党は票を伸ばせず、与党過半数に届きませんでした。「石破おろし」の声もありますが、自民党執行部にとって過半数割れは想定の範囲内であろうというのがBBT大学院・大前研一学長の見方です。「石破おろし」はなぜ実現が難しいのか、大前学長に聞きました。
公明党の弱体化が自民党の大敗を招いた
参院選は開票の結果、与党の自民党は39議席、公明党は8議席だった。自民党は改選前の52議席から13議席減、公明党は14議席減という結果に終わった。非改選議席と合わせると、与党は合計122議席で、過半数の125議席を割り込んだ。2024年10月の衆院選で既に少数与党に転落していたが、連敗により衆参両院共に少数与党となり、今後はますます不安定な政権運営を迫られる。
2024年の衆院選では、政治資金問題で自民党に逆風が吹いていた。今回は目立った逆風はなかったが、だからこそ、現時点での与党の実力が表面化した。
今回与党に勢いがなかった原因の一つは、公明党の弱体化である。公明党は与党入りして以降、「自民党を批判してブレーキをかける」本来の役割を放棄してしまった。公明党が弱体化している原因には大きく二つがある。
(1)過去に神通力を発揮したバラマキに陰り
存在感を示そうと国民に現金や商品券を配る政策には躍起になるが、デジタル後進国の日本では、お金を配るにも事務コストの負担が大きい。「アベノマスク」を配った時の失態を見ても明らかである。
今回の参院選でも物価高対策として1人当たり一律2万円の給付を公約に掲げたが、実際国民に給付する事務を押し付けられることになるのは現場を担う地方公共団体である。熊谷俊人・千葉県知事からもX(旧ツイッター)で批判されていた。現金給付という独自色は、もはや通用しなくなっている。
(2)支持層の高齢化
支持者の高齢化も大きい。選挙には手足となって動いてくれる人が必要で、かつては創価学会信者を中心とした組織力が選挙で役立った。私は1995年の東京都知事選で出馬したとき、公明党とも話をしている。条件がのめずに最終的には応援を断ったが、公明党の組織力の強さを感じてはいた。
しかし、支持者が高齢化して、子どもたちの創価学会離れが進んでいる。公明党の比例代表の得票数はピーク時に900万票近くあったが、今回の参院選は521万票まで減った。これまで自民党が公明党のおかげで僅差を制していた1人区や都市部の複数区で、今回はその上乗せが消え、逆に競り負ける選挙区が相次いだ。厳しい逆風がなくても与党が大敗したのは、公明党の支持基盤が揺らいでいるからである。
過半数割れは想定内。石破政権の狙いとは
ただ、執行部にとって参院選の負けは織り込み済みであり、石破茂首相も退陣のつもりはない。それは選挙後の会見からもよくわかる。石破首相は「比較第一党としての責任を果たす」というフレーズを繰り返した。
「比較第一党」であることを強調したのは、1993年の衆院選後に細川護熙内閣が誕生したことが念頭にあったからにほかならない。当時、宮澤喜一首相率いる自民党は離党が相次ぎ、議席は過半数を割っていた。選挙でも党勢を回復できず、共産党を除く野党が集まって非自民の大連立政権が誕生。自民党は下野せざるを得なかった。石破首相にとって最悪のシナリオは、宮澤内閣の二の舞を演じることだった。
自民党で今回の選挙を取り仕切ったのは木原誠二選挙対策委員長だった。木原選対委員長は岸田前首相の懐刀である。安倍内閣時代から目立たないところで汗をかくのが得意で、安倍政権でも政権存続のために手を打っていた。
参政党は自民党の別働隊
その一つとして噂されているのが、今回議席を伸ばした参政党へのサポートである。石破政権が少数与党になり、残りの野党がすべて集結すれば、1993年と同じように政権交代が起きかねない。それを避ける方法の一つは、野党の中に造反者をつくることである。与党にはくみしないが、野党連合とも一緒にならない勢力が登場すれば、仮に国会で首班指名選挙があっても棄権してくれる。第三勢力が棄権すれば、現状、野党統一候補よりも自民党総裁の得票が上回る可能性が高く、政権交代は起こらない。
今回、参政党は14議席を獲得し、躍進ぶりが話題を集めた。その際、注目すべきなのは、選挙区45人と比例10人、合計55人もの多数の候補者を立てたことである。選挙区の立候補には300万円、比例区には600万円の供託金が必要で、実際の選挙活動にはその10倍程度の費用がかかる。参政党は20億円程度を費やしているのではないか。新興政党がそれだけの資金を準備するのは容易ではない。収入の9割は個人献金としているが、違和感がある。その集金力に対し、「自民党の別働隊ではないか」と噂が立つのは無理もない。
「日本人ファースト」と言って議席を大幅に増やした参政党であるが、極右政党の台頭は世界的な潮流であり、驚くにはあたらない。極右以外の何物でもないな米国のトランプ大統領はもとより、ドイツでは「ドイツのための選択肢(AfD)」が2025年2月の連邦議会総選挙で第2党に躍進して、旧東ドイツを中心とした州議会では第1党になっているところもある。フランスではマリーヌ・ルペン氏の国民連合が一定の支持を得ているし、二大政党で安定している英国でも反移民を掲げるナイジェル・ファラージ率いる「リフォームUK」が急速に支持を伸ばしている。イタリアでは極右と言われ、ムッソリーニに傾注したこともあるメロー二氏がすでに政権についている。
国によって差はあるものの、不満のはけ口を移民、難民、外国人に求める極右勢力は10〜15%程度は存在するもので、今回の参政党の比例代表得票率約12.5%もその幅に収まる。また、参政党支持層は自民党旧安倍派の支持層から流れてきた人が多く、急に排外主義に目覚めたわけではない。
下野したくない自民党の切り札
野党大連立を防ぐ方法がもう一つある。野党を切り崩して与党内に取り込み、連立政権を組むのである。1993年に下野した自民党は翌1994年、水と油だった日本社会党と組み、新党さきがけを加えた「自社さ連立」で政権を奪取した。同じように、公明党に加えてもう一党を取り込めば政権を維持できる。
参政党は影の別働隊として温存しておくとして、自民党のターゲットは玉木雄一郎代表の国民民主党である。玉木代表は財務省出身のわりに、どうも数字に弱いところがある。しかし、政治家にとって致命的であるスキャンダルを経験しても政治的なダメージはほとんどなかった。この打たれ強さには自民党も魅力を感じている。
玉木代表も自分を安く売るつもりはなく、連立するなら「玉木首相」を要求する。これば自民党としても簡単にのめる話ではないが、万が一の時の保険のシナリオとしてはありうる。
日本維新の会も第2候補である。創設者である橋下徹氏が、「『大阪府副首都をのむなら連立に加わる』と打ち出したらどうだ」とささやいている。自民党にとってあわよくば自・公・国・維の可能性があるという点で、石破首相は強気、野党第一党の野田佳彦代表の顔色が冴えないという事情が理解されるのである。
世界の首脳と直接交渉でき、第4の波を駆使できるリーダー
政局の話ばかりをしていると本質を見失う。世界が激動している今、日本を率いるのにふさわしいリーダーについて改めて議論する必要がある。
世界では安全保障のあり方が変わってしまった。「力による現状変更」が黙認され、国連やその他の枠組みを中心とした国際協調主義は通用しなくなった。経済面でも、トランプ大統領の気まぐれにうまく対応できないとダメージを食らう。こうした時代にリーダーに求められるのは交渉力である。もちろん事務方や閣僚レベルの交渉は大切だが、そこでどれほど緻密に積み上げても、トランプ大統領が「No」と言えばひっくり返される。最後はリーダー同士で交渉して「Yes」を引き出す力がなければ、激動の時代を生き抜けないのである。
欠かせないのは英語力である。交渉でこちらの主張を通すには論拠をロジカルに話すだけでは不十分で、抑揚や間を意識して駆け引きする必要がある。交渉を有利に進めたければリーダー自身が英語を操って駆け引きすべきである。
実際、トランプ大統領相手にうまく立ち回っているリーダーは英語がうまい。ドイツのフリードリッヒ・メルツ首相は、ウクライナ支援を渋るトランプ大統領と電話会談して、迎撃ミサイル「パトリオット」をドイツが購入してウクライナに送る話をまとめた。
日本で英語堪能な国際経験者といえば、上川陽子前外務大臣、茂木敏充元外務大臣、林芳正官房長官らハーバード大学ケネディスクール修了組である。トランプ大統領と突っ込んだ話ができるという点では候補に入る。日米貿易戦争華やかなりし頃はソニー創業者の盛田昭夫氏のような経済界の人が活躍したが、今の財界には同じレベルの人材が見当たらない。
加えてリーダーには第4の波―—スマホとAI革命――への対応力も求められる。トランプ大統領は、もはやマスコミを相手にせず、SNSで直接発信している。SNSであればファクトチェックを受けずに好き放題に発信できるからである。発信する内容はデタラメばかりでほめられたものではないが、自信の影響力を強めるという意味では効果を発揮する。まさにスマホとAIのチャンピオンである。日本を見渡すと今回の選挙でSNSをうまく使ったのは参政党である。世界の首脳と直接交渉ができ、かつ第4の波を味方につけるリーダーが現れなければ、日本が国際舞台で復活することは難しい。
※この記事は、『プレジデント』誌 2025年9月12日号を基に編集したものです。
大前研一
プロフィール マサチューセツ工科大学(MIT)大学院原子力工学科で博士号を取得。日立製作所原子力開発部技師を経て、1972年に経営コンサルティング会社マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社後、本社ディレクター、日本支社長、アジア太平洋地区会長を歴任し、1994年に退社。スタンフォード大学院ビジネススクール客員教授(1997-98)。カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)公共政策大学院総長教授(1997-)。現在、ビジネス・ブレークスルー大学学長。豪州BOND大学教授。



