教員不足は、日本の教育を根本から見直すチャンス
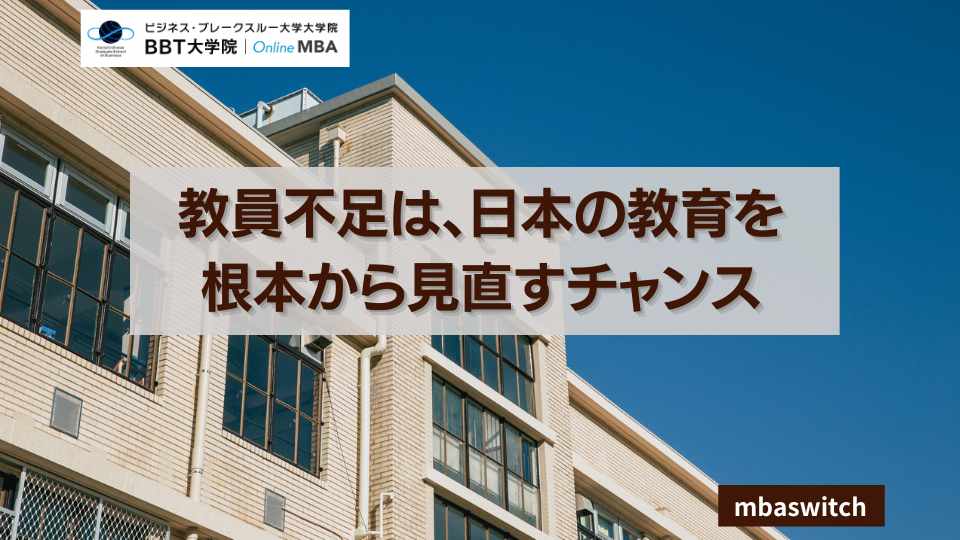
大前研一(BBT大学大学院 学長 / BOND大学教授 / 経営コンサルタント)
編集/構成:mbaSwitch編集部
全国で教員不足が深刻化しています。しかし、欠員を埋めるために「数を増やす必要はない」とBBT大学院・大前研一学長は指摘します。「AI時代になったことを考えると、むしろ教員不足は日本の教育を根本から見直す絶好のチャンス」というのが大前学長の主張です。教員不足を転じて、どのように日本の教育を見直すのか、大前学長に聞きました。
AI時代に「先生」は要らない
全教(全日本教職員組合)は、全国の地方組織に対し教員未配置について聞き取り調査を実施している。回答に応じた36都道府県と12政令指定都市を集約すると、2025年5月1日時点での欠員数は、小学校1478人、中学校1184人、高校418人、特別支援学校514人などで、計3662人にのぼった。
【資料1】
「教育に穴があく(教職員未配置)」実態調査結果(2025年5月1日時点)
各都道府県の教育委員会は、教員免許資格を持たない人に対して、例外的に「臨時免許」を交付して欠員を埋めようとしている。臨時免許があれば最長で3年、授業を担当できる。しょせんは焼石に水である。2024年度の公立学校の教員の採用倍率は3.2倍で、3年連続で過去最低を記録した。ただ、慌てる必要はまったくない。AI時代に「先生」は要らないからである。
まず、インターネットを使えば先生は一人で済む。例えば、大学の経済学の講義では、定番の教科書に沿って進められることが多い。では、授業で何をやるのかと言えば、教科書を読む輪読会である。先生の役目は講釈師で、自分の考えを話すわけではない。講釈師が各学校に就くぐらいなら、一流の経済学者の講義をネットで配信したほうがいい。英語が苦手な人はAIで翻訳すればいい。他の科目も同じである。
高等教育に限らない。初等中等教育にも、それぞれの領域で世界的に第一人者の先生がいる。そうした先生に英語で授業をしてもらえばいいのである。
言葉の心配はいらない。マレーシアのマハティール首相のアドバイザーをしていた当時、マレーシアで国語論争が起きた。英語教育に力を入れないと世界から遅れてしまうが、マレーシア語を軽視するとイスラム教勢力が反発する。相談を受けた私は「各学校に決めさせればいい」と提案した。
すると、ほとんどの学校が物理や数学を英語で、国語と宗教をマレー語で教えるようになった。英語で物理や数学を教えるために、オーストラリアから先生を呼び込んだ。その結果、子供たちは2つの言語で育ってバイリンガルになっていった。英語を教えるのではなく、英語で教える。いまやマレーシアは子供を安価に語学留学させることができ、バイリンガルの教育を受けることができる国として日本でも人気がある。
AI教師のほうが人間よりも優れる
学習は授業を聞くだけでは不十分である。知識や技術は、問題を解いたり反復して練習したりして、習得する必要がある。そこにAI教師を導入するのである。
日本の学校では一人の先生が何十人もの生徒を受け持つので、標準的なレベルに合わせて授業を行わざるをえない。一方、AI教師は1対1の個別指導が可能で、個人の目標と現状の差分をきめ細かく教えてくれる。
全員で同じことを学ぶより、このように自分に合った内容で学習したほうが学力は上がる。一人ひとりに家庭教師をつけるリソースはないのだから、AI教師を導入すべきだろう。
世界トップクラスの一人の先生によるコンテンツ配信とAI教師による個別指導、その組み合わせで教えれば、学力面では何の心配ないどころが、より質の高い教育ができるだろう。
授業以外のところは、クラスにティーチング・アシスタント(TA)を一人つけて面倒みればいい。進路相談に乗る、いじめに目を光らせる、災害時に避難誘導するといった仕事は、やはり人間でなければ務まらない。
ただ、雑務も事務の部分はAIで効率化できるし、モンスター・ピアレンツの対応はAIチャットポッドに任せることも可能である。AIを活用すれば、授業以外の部分も卒業生のアルバイトで十分に務まる。いずれにせよ従来型の先生は不要である。
一方、AI時代の教育で人が足りないところがある。学習指導要領の外側で教える先生である。このコラムで繰り返し指摘してきた。
【資料2】
高校無償化は国を亡ぼす愚策?
日本の学習指導要領は戦後につくられ、その後も約80年、改訂を行いながらも、工業化社会を前提とした指導要領をベースに、今日まで続いてきた。工業化社会には正解があり、それをどれだけ速く、大量に、安くこなせるかが勝負だった。工業化社会の時代は、自分で考えるのではなく、正解を覚え繰り返す教育が成功につながった。
しかし、AI社会は正解が誰でもすぐに手に入る。私の孫は三世代でディナーをしているとその場でパッとスマホをいじって「おじいちゃん、それ間違っているよ」と指摘してくる。生まれたときからスマホに触れ、「染色体にもしみついている世代」は難なく大人と同じ答えにたどりつくのだ。
そうした時代に「正解」に価値はない。当然、正解を身につけさせようとする学習指導要領も時代にそぐわなくなる。AI社会に価値を持つのはAIにはひねり出せない構想やコンセプトをデザインする力である。新しいものを生み出さなくてはいけないのに、正解以外の回答に対してバツをつける教育をすれば。子供は「間違ったことを言ってはいけない」と委縮してしまう。学習指導要領は百害あって一利なしである、
正解ありきの日本の教育を大改革すべき理由
実際、今世界で活躍している日本人は学習指導要領の外側で育った人ばかりである。アニメやゲームのクリエイター、スケートボードのメダリスト、世界的な音楽家、ミシュランの星が世界でもっとも多い都市は東京であるが、料理人も学習指導要領の外側で腕を磨いてきた。正解が決まっていない世界で新しいものを追求してきたからこそ、AI社会でも先頭に立てたわけである。
正解がない世界での問いには、学習指導要領やAIでは対応できない。そこで重要になるのは親の教育である。親は子供に何か聞かれても、すぐに答えてはいけない。まずはAIに聞いて従来の正解を一緒に調べる。そしてその先を二人で考える。つまりティーチャー(先生)ではなく、ファリシテ—タ—(意見を引き出す人)として、子供に自分の頭で考えることを促すべきである。
ところが日本の親は「ちゃんと学校に行きなさい」と子供を学習指導要領の中に押し込めようとする。それでは21世紀を生きる力は身につかない。子供が学校からはみ出たときは、むしろ好きにさせるのが親の務めである。
そのほかに親は道徳や社会のルールを教える必要がある。家庭や社会に対してどのような責任を負うべきか。これも学習指導要領にない領域である。
社会のことは学校でも教えたほうがいい。ただ、正解を示すのではなく、実社会の人を呼んで経験を語ってもらうスタイルがいい。たとえば子供を6人育てたお母さんに来てもらって子育てについて語ってもらう。プログラマーに仕事の中身やプログラミングについて話してもらってもいい。実社会のリアルな姿を教えてもらい、そこから自分が社会でどう生きるのかを考えさせるのである。
また社会人は月に1回は仕事を休んで、自分の生きた知識や経験を子供たちに教えるべきである。「学校を卒業したらもう関わらない」のではなく、教育現場に関わり続けてこそ、コミュニティは強くなる。
ところが、こうした改革を嫌がるのが文部科学省、そして日教組(日本教職員組合)である、文科省は学習指導要領を現場に守らせることに心血を注いでいて、学習指導要領の外側を教える民間人を迎え入れたがらない。
一方日教組は、教員の労働組合であり、自らの失業に繋がりかねないことにはすべて抵抗する。職場に民間人が入り込むことはもちろん反対で、教員免許を持たない社会人を教員にする「特別免許」の活用にも慎重な立場をとる。英語も母国語か英語の国の先生に教えてもらうのが一番だが、日本では正教員とは認められない。英語教育は改革されないままであるため、日本人はいつまでたっても英語が苦手である。同様に、AI活用も本来は仕事の合理化になるはずであるが、教員不要論につながるなら、日教組は猛烈に反対するだろう。
日本の教育は大変革が必要だが、日教組は抵抗勢力の筆頭である。自民党はコメ不足で農協中心の流通にメスを入れた。教員不足を好機として日教組問題にも着手してほしい。既得権益を壊さなければ、日本の教育改革は前進しない。21世紀に世界で活躍できる人材は文科省の下では生まれてこない。
※この記事は、『プレジデント』誌 2025年8月8日号を基に編集したものです。
大前研一
プロフィール マサチューセツ工科大学(MIT)大学院原子力工学科で博士号を取得。日立製作所原子力開発部技師を経て、1972年に経営コンサルティング会社マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社後、本社ディレクター、日本支社長、アジア太平洋地区会長を歴任し、1994年に退社。スタンフォード大学院ビジネススクール客員教授(1997-98)。カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)公共政策大学院総長教授(1997-)。現在、ビジネス・ブレークスルー大学学長。豪州BOND大学教授。



