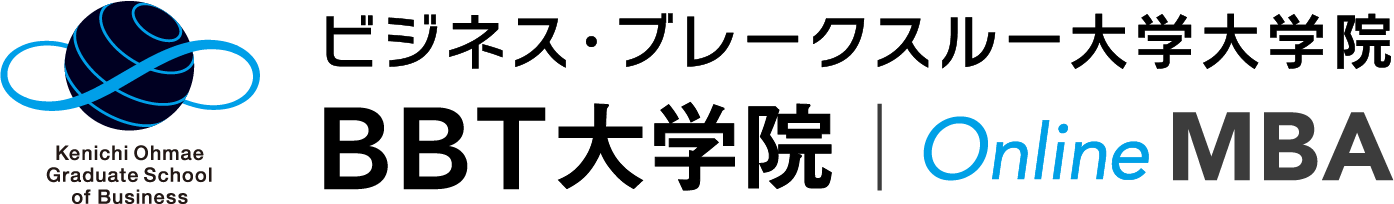本心はイランと戦争したくないトランプ米大統領の腹の内
大前研一(BBT大学大学院 学長 / BOND大学名誉教授 / 経営コンサルタント)
編集/構成:mbaSwitch編集部

米国とイランの関係が緊迫の度を高めています。
仲介役を買って出た安倍晋三首相がイランを訪問したタイミングで、イラン沖のホルムズ海峡を航行中だった日本のタンカーが攻撃を受けました。トランプ米大統領は証拠映像を示してイランの関与を断定しましたが、イラン側は断固否定してします。
そうして両国の軍事的緊張が高まる中、今度はイランが「領空を侵犯した米軍の無人偵察機を爆撃した」と発表した。米国は「飛行していたのは国際空域」と主張、トランプ大統領は「イランは大きな誤りを犯した」とツイートしました。
偵察機撃墜の対抗措置としてトランプ米大統領は限定的なイラン攻撃を一時承認したものの、イラン側に150人の犠牲者が出るとの報告を受けて、作戦実施の10分前に中止を命じたことも明かしています。
ここまでくると、米軍のイラン攻撃は時間の問題のように思えますが、BBT大学院・大前研一学長は「トランプ大統領の戦意は本気ではない」と見ています。
戦争になれば長期化が必至で大統領選にトランプ不利
トランプ大統領は対イラン戦争にまで踏み込まないと私は見ている。なぜならトランプ大統領の頭の中は、2020年2月から始まる大統領選挙一色だからである。このままイランとの戦争に突入したら、選挙戦に不利になるのは目に見えている。開戦1週間程度で決着をつけられるならいいが、イランはそれほど簡単な相手ではない。イラク陣営と米陣営を分析してみると以下のようになる。
(1)イランは大国
イランは大産油国であり、人口約8000万人、国土の広さは世界17位の大国だ。ペルシャ帝国の伝統を受け継ぐ中東の先進国で、国民の教育レベルは高い。イラクを支配していたフセイン政権はイスラム教スンニ派の少数派だったが、イランは最高指導者や国家元首以下、国民の9割以上がシーア派というシーア派大国で、宗教的な団結力や忠誠心は高い。経済制裁に慣れている国民は戦時下の窮乏にもそうそうくじけない。
(2)ロシアや中国がイランに味方する可能性
米国がイランと戦端を開いた場合、「反米」で同調しやすいロシアやシリア、イエメン、さらにはトランプ政権との関係が悪化しているトルコや中国などもイラン側に回る可能性がある。直接イランに関与しなくても、この機に乗じてフーシー派やイスラム過激派がテロ活動を活発化させることも十分に予想できる。
(3)米国に味方する国は一枚岩でない
湾岸戦争、イラク戦争、アフガニスタン派兵のときのように米国に協力して出兵する国があるだろうか。
まず欧州勢は協力しそうにない。トランプ政権がイラン核合意(米英仏独露中とイランによる2015年の合意)を勝手に離脱したことが一つの発端だからだ。少なくとも、イランとの経済的な結びつきが強いフランス、ドイツなどは動かないだろう。
イランを敵視するイスラエルは間違いなく米国に同調する。しかし、やっとのことで総選挙に勝利した右派ネタニヤフ政権は盤石ではなく、汚職スキャンダルに揺れている。イスラエルはハマスなどのパレスチナ武装組織との戦いは得意だが、越境して空爆したなどの例外はあっても、イランと直接戦争した経験はない。対イランとなると、いくつかの国が中間にあるので、構えるところがあるのだ。従って、イスラエルが米国と組んでイラン相手にドンパチやるシーンは考えにくい。
周辺国で言えば、米国から兵器を大量に買っているサウジアラビアは一貫して「金持ち喧嘩せず」を貫いてきた。従って、後方支援に回ることはあるだろうが、直接前面に出るとは考えにくい。
米軍が駐留するイラクもイランとの開戦を望んでいない。イラク領内にはイランが支援するシーア派民兵が多数入り込んでいて、米国とイランが激突すれば、再びイラクが戦火にさらされる危険性が高い。せっかく安定化してきたイラクがまた不安定化しかねないということで、米国内ではイラン攻撃を回避させるためのロビー活動も盛んに行われている。
(4)米国内情勢
1979年に起きたイラン革命はシーア派の宗教指導者ホメイニ氏による宗教改革だったが、これを嫌って国外脱出したイラン人が大勢いた。米国に逃げてきた人もいる。彼らは比較的インテリが多く、米国内で一定の影響力を持っている。米国にもイランにシンパシーを持っている人がそれなりにいるのだ。
大統領選を戦うため、トランプ主役の物語をプロデュースしているだけ
再選が最大の関心事のトランプ大統領は上記のような国外情勢や国内情勢に目を配っているし、自らの大統領選にとって対イラン戦争が長引くのは得策でないこともわかっている。トランプ大統領の腹の内は「戦争回避」なのだ。実際、「イランと戦争しようとは思わない」「前提条件なしで協議する用意がある」と公言している。
トランプ大統領は戦争になった場合、「かつて見たこともないような完全破壊が起きる」「ANNIHILATION(国家の消滅)」という、あまり外交では使わない過激な言葉を用いてイランをけん制する。こうした相反する言動は、トランプ流の劇場(激情)型政治ととらえると理解しやすい。
イラン問題は、プロデューサーであるトランプ大統領の演出が随所に垣間見れる。イラン合意を離脱して、対イラン経済制裁を再開した第1幕は、トランプファミリーと縁の深いユダヤ人国家イスラエルと、武器を大量に買ってくれるお客さん=サウジアラビアへのサービス。もちろん、大統領選に向けた国内のトランプ支持派に対する露骨なアピールである。
第2幕で屈強なイランと本格的な戦争に突入する意思はないし、大統領選にも不利に働く。従って、イランには寸止め。それでも「オレは言うことは言った。国連やイラン合意では核開発は止められない。だからオレがイランにタガをはめてやった」と自分が主役の物語にできれば選挙を戦えるのだ。
※この記事は、『プレジデント』2019年8月2日号pp.82-83を基に編集したものです。
大前研一
プロフィール マサチューセツ工科大学(MIT)大学院原子力工学科で博士号を取得。日立製作所原子力開発部技師を経て、1972年に経営コンサルティング会社マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社後、本社ディレクター、日本支社長、アジア太平洋地区会長を歴任し、1994年に退社。スタンフォード大学院ビジネススクール客員教授(1997-98)。カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)公共政策大学院総長教授(1997-)。現在、株式会社ビジネス・ブレークスルー代表取締役会長。ビジネス・ブレークスルー大学学長。豪州BOND大学名誉教授。