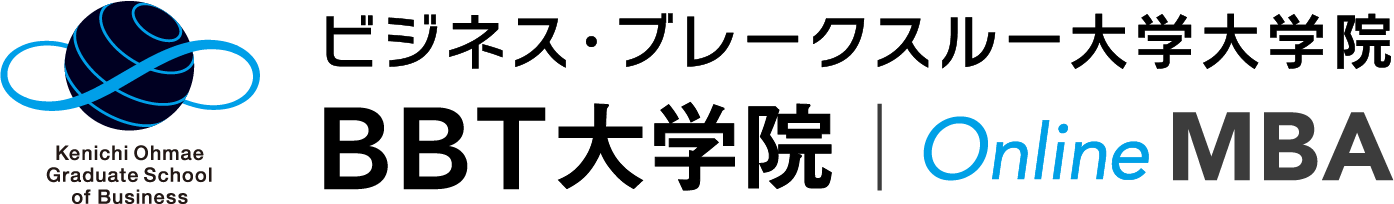中曽根元首相の約1億円葬儀は妥当だったのか?

大前研一(BBT大学大学院 学長 / BOND大学教授 / 経営コンサルタント)
編集/構成:mbaSwitch編集部
2019年11月に101歳で大往生した中曽根康弘元首相の内閣・自由民主党合同葬儀が、2020年10月17日、執り行われました。葬儀費約9600万円を20年度予算の予備費から捻出することに一部批判がありましたが、「中曽根元首相の功績を鑑みれば妥当の域を超えるものではなかった」とBBT大学院・大前研一学長は言います。
外交では日米イコールパートナー関係を築く
中曽根氏は20代の陣笠議員の頃から「総理大臣になりたい」という強い信念があった。首相公選制を最初に提起したのも中曽根氏だ。
ドイツの名宰相ヘルムート・コール元首相は、学生時代から自分がリーダーになって祖国統一を成し遂げたいと強く念じていてそれを実現したが、中曽根氏も似たようなところがある。出征と敗戦、占領統治を経験した中曽根氏の当初の政治目標は祖国再建であり、国家として真の独立を勝ち取ることだった。念願の首相に就任して強くこだわったのは、日米関係をイコールパートナーに持っていくことだった。
日米イコールパートナーなど、当時としては超背伸びした話で、それまではどちらかといえば米国に卑屈にへりくだるか、復讐心を押し殺すような態度の政治家が多かった。しかし体格的に見劣りせず、頭脳明晰で語学も堪能な中曽根氏は、まったく気後れすることなく諸外国とのリーダーと対等に渡り合った。ロナルド・レーガン米大統領(当時、以下同)との間で「ロン・ヤス」と呼び合うような信頼関係を築き、サミットの記念撮影ではレーガン大統領と肩を並べて中央に収まった。この写真は日本の国際的地位向上を内外に印象づける一枚になった。
中曽根氏はパフォーマンスに長けたリーダーだった。私が行きつけのホテルのジムや環七沿いのテニスコートに新聞記者を引き連れてよく現れたものだ。それが身体能力の高さにも直結していたわけだが、首相を辞めた途端にどちらにもパタリと来なくなった。首脳会談で来日したレーガン大統領夫妻を別荘(日の出山荘)に招き、囲炉裏の前で亭主としてお茶をたててふるまったのも、中曽根氏らしい演出だった。
内政では行財政改革を断行
華々しい外交の一方で、内政最大の功績はやはり行財政改革である。レーガン大統領や英国のサッチャー首相(当時)にならって、規制撤廃と3公社、つまり日本国有鉄道(現JR各社)、日本電信電話公社(現NTT各社)、日本専売公社(現JT)の民営化を断行した。
当時の公社、特に国鉄は組合の巣窟で民営化に激しく抵抗していたし、電電公社も民営化決定後に組合の残党が長々と日比谷本社前で闘争を続けていた。中曽根氏は、「ミスター合理化」の異名を持つ財界の重鎮・土光敏夫氏を臨時行政改革推進審議会(行革審)のトップに据え、土光氏から国鉄再建管理委員会の委員長を託された亀井正夫氏(住友電工元会長)らとともに、文字どおり命がけで民営化を成し遂げた。亀井氏の元には脅迫や嫌がらせが殺到して、自宅に半年以上も帰れない状況が続いたそうだ。
時代とともに果たすべき公共性を失い、債務を膨らませて国の重荷になり下がったとはいえ、国鉄や専売公社は地域雇用の大きな受け皿でもあった。これを民営化するエネルギーは並大抵ではない。しかし中曽根氏は3公社の民営化を見事に完遂して、これが後の小泉純一郎政権の郵政民営化などにもつながった。中曽根内閣が掲げた「戦後政治の総決算」というスローガンに違わない仕事ぶりだったと思う。
大前研一は中曽根氏の選挙参謀だった
中曽根氏と私の出会いは、外務省出身の首相秘書官だった長谷川和年氏から電話をもらったことだった。「日米関係についてアドバイスしてほしい」と言われて、ある日、高級料亭でお会いした。当然、先方のおごりだったのだが、おごってもらった気がしないほどの質問攻めである。
中曽根氏は胸のポケットから質問が書かれたメモを取り出して「これはどう考えたらいいですか?」と質問してくる。私が説明している間に中曽根氏は料理をパクついて、一息つくと走り書きして「大前さんの言っていることは要するにこういうことですね」と確認する。
これがまた的確な要約で「そうです」と答えると、「儲けた!」と言ってすぐに次の質問を投げてくる。そうやって5つか6つの質問を終えると「じゃあ、今日はこれで」。おかげでこっちは料理に手を付ける暇もない。
的を射た質問ばかりだし、打てば響くような理解力も素晴らしかった。首相経験者から若手までいろいろな政治家と話をしたが、「話が難しい」と上から目線の政治家もいれば、竹下登元首相のように自分をまず卑下して相手を立てて話題に入る政治家もいた。中曽根氏にはそういう上下の視線がまったくない。34歳年下の私の話を真剣に聞き入って何かを得ようと、若々しい気迫に溢れていた。
そんな中曽根氏だから、総選挙の戦い方をこちらから提案したこともある。
田中角栄氏がロッキード事件の第一審で有罪判決を受けたことで政治倫理が大きな争点となり、1983年の総選挙で自民党は単独過半数を割る敗北を喫した。中曽根氏は86年の総選挙で巻き返しを期したが、メディアの事前の票読みでは形勢不利が伝えられ惨敗の可能性すらあった。
そこで私が提案したアイデアが「衆参ダブル選挙」だった。当時は投票率が下がり続けていて、組織票を持つ政党が有利な状況だった。投票に行かない有権者を分析すると、圧倒的に自民党支持が多い。
「日本は変わらない」「自民党政権は永遠に続く」と思うから投票に行かないのであって、隠れキリシタンならぬ隠れ自民党支持者となっていた。彼らを投票所に駆り出せば自民党は圧勝できる。物理的に投票率を上げる秘策が衆参同日のダブル選挙だったのだ。本当は統一地方選も含めたトリプル選挙を中曽根氏に進言したが、「それは勘弁してくれ」とのことだった。
選挙参謀として自民党の区割りや候補者調整にも知恵を貸した。要するに選挙区ごとに綿密なマーケティング分析をした。中選挙区で複数擁立している自民党の一方の候補者が票を取りすぎると、2位に野党が入り「死に票」が発生する。自民党の得票が最大の議席数につながるように区割り調整まで提案させてもらった。この辺りの事情は『大前研一の新・国富論』に詳しい。
結果、86年の衆院選挙は自民党が304議席を獲得して圧勝、単独過半数を回復した。
中曽根氏以降は、再び「米政府霞が関出張所長」に逆戻り
中曽根政権後は、海部俊樹内閣のときに中曽根氏が目指した日米イコールパートナーを辱めるような外交が行われていた。私はそういう海部首相のことを『米政府霞が関出張所長』と揶揄して雑誌で批判したことがある。
これを読んだ中曽根氏は相当喜んだらしく「久しぶりに飯を食おう」と連絡がきて、2人で海部首相の悪口を言って盛り上がった。
安倍前政権でも対米隷属で、中曽根氏以前の日米関係にすっかり戻ってしまったが、その現状に天上から中曽根氏の嘆息が聞こえてきそうである。
※この記事は、『プレジデント』誌 2020年12月4日号 を基に編集したものです。
大前研一
プロフィール マサチューセツ工科大学(MIT)大学院原子力工学科で博士号を取得。日立製作所原子力開発部技師を経て、1972年に経営コンサルティング会社マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社後、本社ディレクター、日本支社長、アジア太平洋地区会長を歴任し、1994年に退社。スタンフォード大学院ビジネススクール客員教授(1997-98)。カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)公共政策大学院総長教授(1997-)。現在、株式会社ビジネス・ブレークスルー代表取締役会長。ビジネス・ブレークスルー大学学長。豪州BOND大学教授。