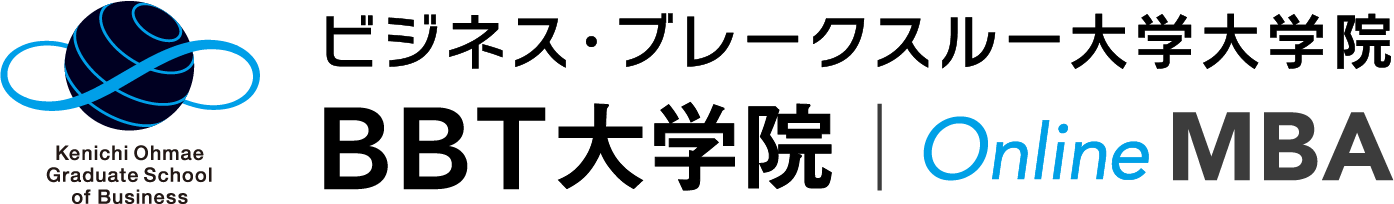日本人の所得はなぜ増えないのか?

日本の初任給はこの30年間、24万円前後でほぼ横ばいが続いています。その間に欧米では3倍ほどになっています。「日本では就職や転職に対する考え方が世界標準からズレているのが原因」とBBT大学院・大前研一学長は指摘します。
大前研一(BB大学院 学長 / BOND大学教授 / 経営コンサルタント)
編集/構成:mbaSwitch編集部
「より高い給料を求めて転職する」という発想がない
IT技術者は、海外では給料が高い職業だが、日本では初任給が24万円前後と他職種と変わらない。中国はじめ世界のIT業界では、「給料が安い日本の技術者を雇うのが最も得」だと言われている。
インドのIT技術者は、20代で年収1600万円も珍しくないから、日本とは5倍の開きがある。インド工科大学は23校あって、IT技術者も数多くいる。日本からバンガロールなどに採用担当者を派遣しても、日本企業に就職したがる技術者はほとんどいない。世界中から年収1600万円で声をかけられるのだから当然だ。
しかも、日本の採用担当者は「年収300万円だけど、ライフタイム・エンプロイメントで、毎年のように昇進昇格するよ」と勧誘する。「インドのIT技術者が、終身雇用を望んでいる」と勘違いしているのだ。世界のIT技術者は、転職を繰り返して出世していく。終身雇用に魅力を感じるわけがない。
IT業界に限らず、日本では就職や転職の考え方が、世界標準からズレている。より高い給料を求めて業種を超えて転職するという発想がない。日本の給料が安い原因の1つだ。
日本で平均年収が高い企業といえば、キーエンスが筆頭にあがる。過去5年の平均は2000万円に近い。しかし、キーエンスに転職希望者が殺到しているという話は聞かない。
米国にキーエンスのような企業があれば、間違いなく就職希望者が殺到する。海外では「あの会社は給料が高い」と聞けば、みんなが転職しようと考えるのが常識だ。しかし、日本人は「いいなぁ」と羨ましがるだけで自分の問題として考えない。日本では人ごとになってしまうところに問題がある。
転職が当たり前の国では、企業も給料の高さを競って、優秀な人材を採用し、辞めていかないようにする。需要と供給によって、給料は自然に上がっていくものである。
転職しないから所得が上がらない
日本では、政府が最低賃金を指図したり、経済団体に賃上げを要請したりする。まるで共産主義社会だ。上から目線で無理に給料を上げさせれば、企業は潰れかねない。
日本人はいったん就職したら、給料が上がらなくても、なぜか転職しない。そのくせ同じ会社の同期と少しでも差がつくと胃潰瘍になるくらい悔しがる。給料が高い会社に移ろうと必死にもがくことがない。働く人の多くが必死にもがいたら、米国と同じ水準の給料になっていただろう。
米国には3つの転職がある。(1)会社を移る転職、(2)地域を移る転職、(3)業界を移る転職の3つである。
(1)会社を移る転職
転職で最も容易なのは、同業他社に移ることだ。だから多くの会社は、辞めても5年間は同業他社に就職してはならないというルールを設けている。5年経つまで、タクシードライバーなどで食いつなぐ人たちもいる。
(2)地域を移る転職
地域を移る転職は、米国では地域の給与格差があるからだ。東海岸、西海岸に比べて、中西部、南部、テキサス州などは給料が安い半面、所得税がないなど生活費はかからない。昔は西へ西へと向かったが、いまは両岸の物価が高すぎるから、テキサスなどで暮らす人も増えている。
(3)業界を移る転職
業界を移る転職は、米国は業界の給与格差が大きいから当たり前に行われる。例えばIT技術者なら、製造業から金融業界に転職すれば給料は跳ね上がる。
このように米国は(1)会社、(2)地域、(3)業界を移る転職によって、国全体で人材が交ざり合って活気づいている。この転職のためのデータも豊富に揃っているし、リンクトインなどでも具体的な転職の話にありつける。
上昇志向がないことは、日本の深刻な問題である。
40代後半から50代まで給料のピークを迎えても、レジャーなどに使わなくて貯金にまわしてしまう。その結果、個人金融資産は約2000兆円。30年前と比較してGDPが伸びないまま、個人金融資産だけが2倍近くになっている。そのうち半分の1000兆円ほどが現金・預金で、預金は0.01%しか利息がつかない。私が言う“低欲望社会”は、日本の給料が上がらない根本原因だ。
海外では、給料が高い仕事に就くために、外国に移住することも珍しくない。コンピュータ言語と英語ができれば、米国へ渡ってGAFAに転職しようと考える。しかし、日本では海外に行って稼ごうと必死にITと英語を勉強する人はほとんどいない。
脱・低欲望社会の鍵を握るのは親の教育
とはいえ、現在でも世界を目指す意欲的な人間は日本でも育つ。鍵は、親の教育だ。
例えば、バイオリニストの廣津留(ひろつる)すみれさんだ。
彼女は2歳でバイオリンと英語を習いはじめ、4歳で英検3級に合格した。高校まで地元の大分市に住んで公立の学校に通い、16歳のときにカーネギーホールでソロデビューしている。その後、ハーバード大学に進もうと決め、高校3年の12月に合格した。ハーバード大学では応用数学、社会学などを勉強して、主専攻は音楽を選んだ。2016年にハーバード大学を首席で卒業すると、ニューヨークにあるジュリアード音楽院の大学院に進学し、ここでも首席で卒業した。
廣津留すみれさんが幼い頃から音楽と英語に打ち込んだのは、母親の真理さんが上手に導いたからだ。英語塾を主宰する真理さんは、日米の育児書を200冊ほど読み込んで独自の教育方針を立てたそうだ。
廣津留すみれさんを見ていると、親のオリエンテーションが重要であることがよくわかる。イチロー、タイガー・ウッズなど、親が熱心だったスポーツ選手と同じである。音楽でもスポーツでも文科省の指導要領の範囲外で良いコーチに恵まれれば、今でも世界的なレベルに達する。
司馬遼太郎の言う「坂の上の雲」を目指している頃は問題がなかった。戦後の成長期もいい学校を出ていい企業に就職すれば昇進と昇給があった。ところが、ここ30年くらいは学習指導要領どおりの教育をする普通科に通って大学に進学し、新卒一括採用でサラリーマンコースを目指す人材の“低欲望”が、日本人の所得が伸びない最大の原因となっている。
私が若い頃は、小田実のエッセイ『何でも見てやろう』、小澤征爾の『ボクの音楽武者修行』、テレビ番組の『兼高かおる世界の旅』などで海外への夢をふくらませたものだ。現代の子どもたちも、まずは親がいい刺激を与えていけば、世界へ羽ばたいていけるはずだ。そういう親が増えていけば、日本の国力向上につながるということに早く気が付いてほしい。
※この記事は、『プレジデント』誌 2021年12月17日を基に編集したものです。
大前研一
プロフィール マサチューセツ工科大学(MIT)大学院原子力工学科で博士号を取得。日立製作所原子力開発部技師を経て、1972年に経営コンサルティング会社マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社後、本社ディレクター、日本支社長、アジア太平洋地区会長を歴任し、1994年に退社。スタンフォード大学院ビジネススクール客員教授(1997-98)。カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)公共政策大学院総長教授(1997-)。現在、株式会社ビジネス・ブレークスルー代表取締役会長。ビジネス・ブレークスルー大学学長。豪州BOND大学教授。